Q1
そもそも資源やエネルギーの問題が、なぜ世界的に重要な課題になっているのでしょうか。



#1
理工学部 教授
峯元 高志
2024 / 10 / 24
最近、改めて太陽電池がホットトピックになっています。注目を集めているのが、峯元高志フェローが研究している「ペロブスカイト太陽電池」。“日本の再エネ拡大の切り札”とも言われているこの新しい太陽電池の可能性と、私たちが地球の未来にできることについて、峯元フェローのナビゲートで探ります。
SCROLL
about Takashi Minemoto
軽量でフレキシブルなペロブスカイト太陽電池の実用化に向けて
脱炭素社会の実現に不可欠な再エネ分野において、軽量・フレキシブルな結晶構造の材料を用いた新しいタイプの太陽電池「ペロブスカイト太陽電池」の高効率化と高耐久化の両立に挑戦します。要素技術を開発し、劣化メカニズムを解明、寿命予測技術の確立を目指します。企業と連携し、実用化に貢献します。
1997年、立命館大学理工学部から飛び級で同大学理工学研究科へ進学。 2001年、博士課程後期課程修了後、アメリカ・デラウェア大学にポスドク研究員として赴任。 2004年、立命館大学理工学部講師に就任。 2011年、理工学部准教授、2015年から現職。
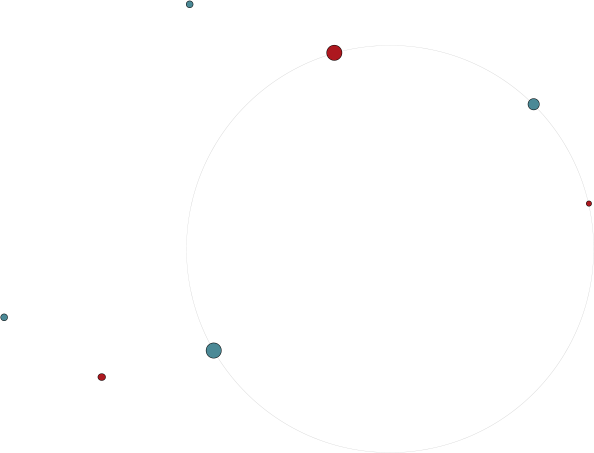




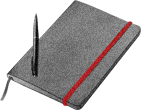


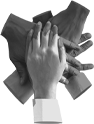
Q1 そもそも資源やエネルギーの問題が、なぜ世界的に重要な課題になっているのでしょうか。
Q2 太陽電池についてのニュースや企業広告をよく見るようになりました。なぜ近年、太陽電池が注目されているのでしょうか?
Q3 最近よく耳にする「ペロブスカイト太陽電池」の可能性と課題を教えてください。
Q4 2030年に向けた太陽電池の未来、広がる可能性と、解決すべき課題を教えてください。
Q5 現代を生きる私たちは、エネルギー問題にどう向き合っていくと良いと思いますか。




持続可能な社会の構築が急務だからです。 2050年までに世界人口は約100億人に達すると予測されています。エネルギー需要が急増するなか、石油などの化石燃料に依存した供給により、CO₂(二酸化炭素)など温室効果ガスの排出量が増加し、地球温暖化を引き起こしています。 これにより、極端な気候変動による海面上昇、自然災害などが増加し、世界中の人々の生活に深刻な影響を及ぼしています。近年の夏の暑さに危機感を抱いている人も少なくないのではないでしょうか。




化石燃料は限りある資源で、ずいぶん先のことですが枯渇リスクはゼロではなく、特定地域への依存により、国際的な緊張も発生してきました。エネルギー安全保障が重要課題になっています。 日本のエネルギー自給率は約1割程度で、主要先進国の中で最も低い水準にあります。特に日本は天然ガスの輸入依存度が高く、供給不安に直面しています。 再生可能エネルギーの開発と持続可能なエネルギーシステムへの移行、エネルギー効率の向上が国際的な 優先課題となっている のです。




温室効果ガス世界資料センターが世界各地の観測データを収集し解析した大気中CO₂の世界平均濃度の経年変化。世界的に上昇しています。





OECD(経済協力開発機構)諸国と比べても、日本のエネルギー自給率は38カ国中37位と、低い水準となっています。









近年、太陽電池が注目されている理由は、環境への配慮と、発電効率の上昇、そして、劇的な低コスト化にあります。 気候変動対策と脱炭素に向けて、また近年の地政学的な緊張などにより、世界各国が再生可能エネルギーの導入を進めています。中でも太陽光発電は最も有望な選択肢です。CO₂排出を抑え、化石燃料に依存せず持続可能なエネルギー供給を実現する手段です。 太陽電池は使われていない土地や建物の屋根などに設置できるため、水力や風力に比べて設置の柔軟性があり、運用開始までのスピードが早く、メンテナンスが比較的容易なのが 特徴です。




日本は、中国とアメリカに次ぐ世界で第3位の太陽光発電導入国です。国土面積当たりの太陽光設備容量は主要国の中で最大です。日本の太陽光発電の総設置容量は2011年から2021年の10年間で10倍以上に成長。




さらに固定価格買取制度(FIT)や市場連動型のプレミアム価格制度(FIP)などの政策が大きな要因となり、住宅用から大規模なメガソーラーまで、幅広い導入が進んだことによります。




日本の太陽光発電導入量はこの10年ほどで急速に拡大し、今後の成長も期待されています。





近年、技術革新により、主流のシリコン系太陽電池の変換効率が向上し、また、プロセス技術の進展と大量生産によってコストが 大幅に削減されたことも、注目を集めている理由です。企業や個人が太陽光発電を導入しやすくなり、普及が加速しています。 太陽電池の普及に伴い、小型化や高効率化のニーズが増えて います。 私たちの研究室では、太陽電池の展開先を拡げることができるペロブスカイトなどの薄膜太陽電池や、 太陽電池モジュールを屋外に設置して、実際の発電挙動を研究しています。








ペロブスカイト太陽電池は、無機と有機のハイブリッド材料の太陽電池です。2009年に桐蔭横浜大学の宮坂力特任教授が発見しました。 エネルギー変換効率が26%を超えるという報告もあり、近年最も伸び率が高い太陽電池だと言われています。 従来型の結晶シリコンの太陽電池パネルは1㎡あたり11kgぐらいの重量があり、重さに耐えられないところには置けません。薄くて軽く、柔軟で、曲面にも設置できるため、都市部の高層ビルの壁面や車の屋根にも貼り付けられる可能性があります。国土が狭い日本でも再生エネルギーの導入を拡大できる有力な選択肢として期待されています。




ペロブスカイトの構造(画像①)。AにはCH₃NH₃などの有機材料が入り、BにはPb, Snなど、XにはI, Brなどが入ります。
ペロブスカイト太陽電池の構造(画像②)。ガラス基板から光を入射するsuperstrate構造になっています。





ペロブスカイト太陽電池のスピンコートによる作製(画像③)
できたペロブスカイト膜(画像④)
結晶シリコン太陽電池の発熱解析(画像⑤)





ペロブスカイト太陽電池は「塗って乾かす」だけで簡単につくることができます。印刷することも 可能です。政府もその開発に力を入れ、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)グリーンイノベーション基金(GI基金)で社会実装に向けて大型助成がなされています。企業の研究開発や実証実験、資金調達も盛んです。 私自身もGI基金事業として、ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化に取り組んでいます。




現在の製造コストは高いのですが、液体を塗るだけで製造でき、印刷も可能になってくると、 今後は結晶シリコンと同等か、より安価に製造できるのではないかと言われています。 結晶シリコンに代わる、未来の太陽電池を日本の研究と日本の技術で実現できるかもしれません。 主な原料となるヨウ素も日本で製造できるので、メイド・イン・ジャパンの太陽電池で国内の電力供給を補うほか、世界にも広げていきたいと、政府 や行政機関も後押ししているのです。




富士経済がまとめた「2024年版新型・次世代太陽電池の開発動向と市場の将来展望」では、“新型・次世代太陽電池の本命”として、ペロブスカイト太陽電池市場が2040年までに大きな成長を遂げると予測しています。





一方で、課題もあります。 ペロブスカイトの太陽電池は研究室レベルでは高性能だと言われていますが、劣化の問題があります。私たちは太陽電池の専門家として、 設計や性能評価を手がけ、劣化のメカニズムを理解したり、劣化を予測したり、抑制する方法を探ったりしています。 性能を落とさずに耐久性も落とさない方法を見つけて実用化までしっかり繋げていかないといけない。その ためにも、我々研究者・専門家の知見を広く役立てていかないといけないと思っています。








太陽電池の未来には、多くの可能性が広がっています。技術の進展により、太陽電池の効率が向上し、より効率的で安価なエネルギー供給が可能になると考えられています。 特に、ペロブスカイト太陽電池やその他の新素材を使用した太陽電池の技術が進化すれば、エネルギーコストが大幅に削減され、個人や企業が太陽光発電を導入しやすくなるでしょう。製造の簡単さ、高い変換効率、設置の柔軟性において進化した太陽電池が屋根やビルの壁だけでなく、さまざまな形状のものに組み込むことができるようになれば、エネルギーの自給自足が可能な未来も夢ではないかもしれません。




国の目標では、再生可能エネルギーの比率は2030年度に36~38%程度になることを目指しています。太陽光発電は全体の14~16%程度を目指すとされ、その成長が期待されています。





しかし、課題もあります。ペロブスカイト太陽電池は長期使用における劣化が大きな課題。劣化メカニズムの解明、耐久性の向上と量産技術の確立が、2030年までに実用化を実現し、太陽光発電の比率を伸ばす鍵となっています。 既存の結晶シリコン太陽電池に関する不具合や危険を回避し、 安全性や信頼性を高めることも重要です。また太陽光発電は天候に依存するため、安定したエネルギー供給のためには、蓄電技術や新たな電力供給システムの整備が不可欠です。太陽電池の製造過程における環境負荷やリユース・リサイクルの課題も解決が必要です。 これらの課題をクリアすることで、太陽光発電は持続可能なエネルギーとして発展を遂げるでしょう。








私たちに求められているのは、個人レベルから企業・団体、そして国家、国際社会まで、多層的な取り組みです。 まず、私たち一人ひとりがエネルギーを無駄にしないよう、環境に配慮したライフスタイルへの移行が求められます。省エネ家電や公共交通機関の利用、 カーシェアリングの利用、消費の見直しなど、エネルギー消費を最小限に抑える生活スタイルを一つひとつ検討していくことが必要です。 家庭でも、企業でも、太陽光や風力などの再生可能エネルギー を積極的に利用し、化石燃料への依存を減らしましょう。 政府も企業も、再生可能エネルギーの導入を促進する政策や 技術開発をさらに進めていく。エネルギー問題は地球規模の課 題であり、国際的な協力も不可欠です。




私のビジョンとしては、太陽電池の専門家として、研究や発信活動、技術者のサポートやコラボレーションを通じてその進歩を後押しし、太陽光発電がどんどん社会に浸透し、私たちの身近なところにやってくることを目指しています。 太陽光発電を社会でうまく利用して、サステナブルに回していくことにも取り組んでいきます。幅広く「太陽電池といえば立命館」 と言われるような活動をしていきます。 人間がこれまで掘り出して使ってきて、大気中に撒き散らしてしまったCO₂を、最終的には今から何百年かけて元に戻して、地球を元の状態に戻さないといけない。これは人類の意志であり、 きっと、地球の意志ではないでしょうか。その一つの手段が太陽光発電であり、その進化や発展のため、力を尽くしていきます。



